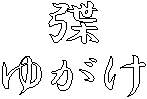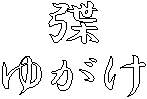| 四つがけの製作工程(本体) |
|
ゆがけの製作工程を写真で示します
必ずしも工程順では有りません |
工程は並行して進む部分もあります |
 |
革の選別(写真提供:鹿革専門会社)
専門会社のご厚意により、数十枚の革の中から
良いものを選びます |
 |
今回は、左の2枚を選び、
燻し加工を依頼しました
家紋を付ける場合は、この時点で依頼します |
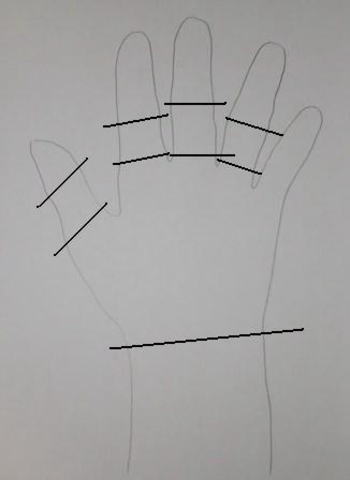 |
採寸・型紙起し
採寸(実際のものではありません)
実線で示した部分等を採寸します |
 |
型紙(実際のものではありません)
採寸の寸法に合わせ型紙を作成します |
 |
鹿革準備
鹿革の専門店に
家紋の型紙(部品参照)を持参し、
数十枚の白革の中から
最適の1枚を選び出します
家紋を付ける場所を決め、
燻し加工を依頼します
革1枚がゆがけ1個分です
但し、大紐はこの革から取れません
物差しは65Cm迄写っています |
 |
裁断
型紙等に合わせ、粗く切断します
革の大きさ、傷の状況等により
各部分を適宜配置します
その後、台革を型紙に合わせ裁断します
添え指部分も型紙に合わせ裁断します |
 |
指縫い
裏から指を縫います
次の写真からは詳細です |
 |
指の腹の折り返しを縫います |
 |
人指し指から親指にかかる部分を縫います |
 |
人指し指と中指の間の補強を縫いま付けます |
 |
指を縫います |
 |
反対側から |
 |
親指付け根を輪にし縫い付けます |
 |
反対側から |
 |
さらに、表をまつります |
 |
拇指の内側になる部分を縫い付けます
左側から |
 |
右から |
 |
指先へ |
 |
反対側から |
 |
指の綻(ほころ)び止めを施します
2回回して |
 |
2本まとめて2、3回巻き止めます |
 |
裏返し(裏から表に返す)
鏝(こて)で縫い目を締めます
腰張り
鏝で一ノ腰、二ノ腰部分を成型します |
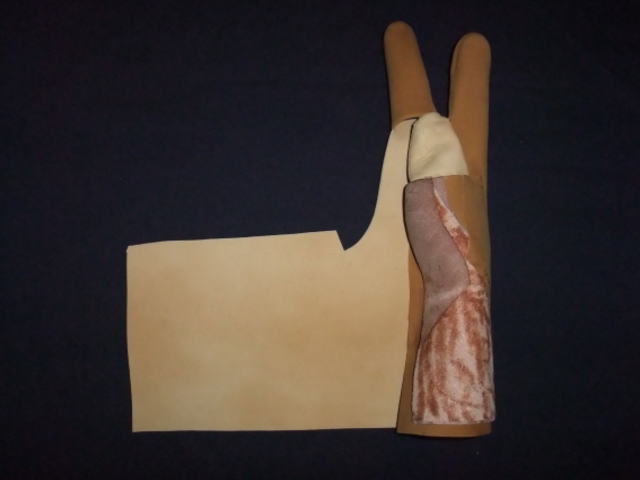 |
床革(部品参照)を貼り腰を固めます |
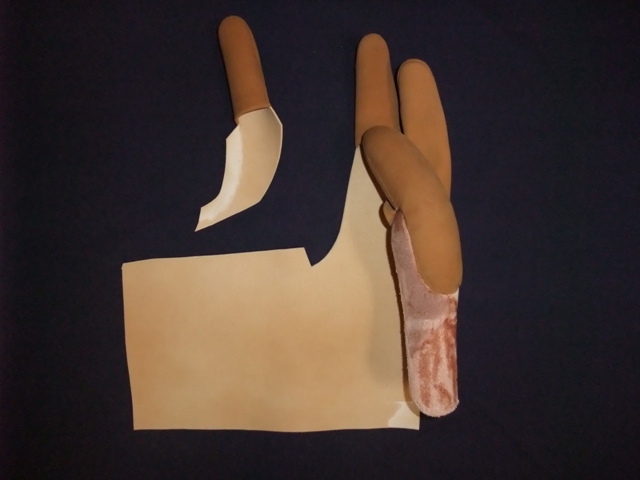 |
腰の不要部分を切り落とし、
帽子(部品参照)を据え付けます |
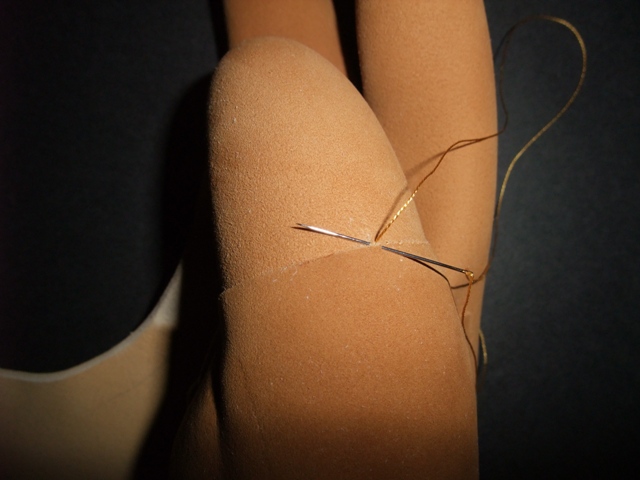 |
控(ひかえ)を張り付け、
控の縁(一の腰)を縫い付けます |
 |
控の縁(甲部分)を縫い付けます
写真は拇指が手前(下向き)です |
 |
小紐取り付け
小紐(部品参照)を取り付けます
(縁を折り返すので、ここで小紐を付けます)
手形に合わせ取り付け位置を決めます |
 |
小紐の厚さ分切り込みます |
 |
切り込みの確認 |
 |
控え革を貼りつけた後取付場所をマーク |
 |
控え革に切り込みを入れます |
 |
小紐を切り込みから差し込み、接着します |
 |
小紐を引き戻したところ |
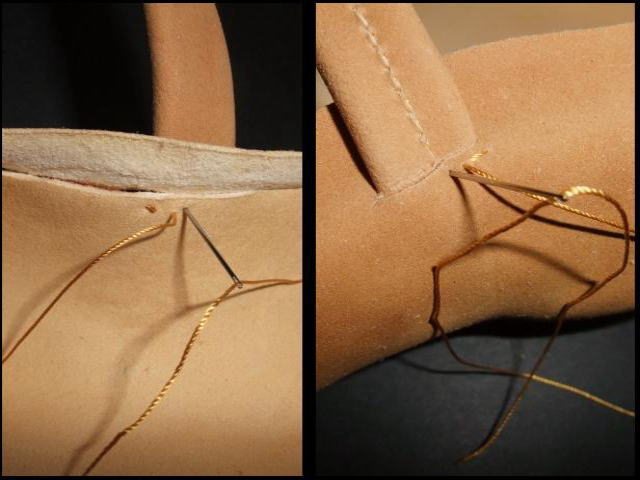 |
小紐を縫い止めます
(この後、縁を折り返します) |
 |
控(ひかえ)を張り付け、
小紐を取り付けたところ |
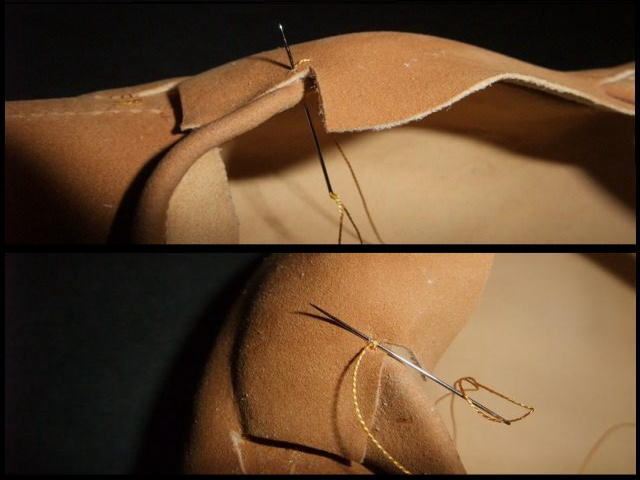 |
控えの縁(脈所部分)に綻び止めを施します |
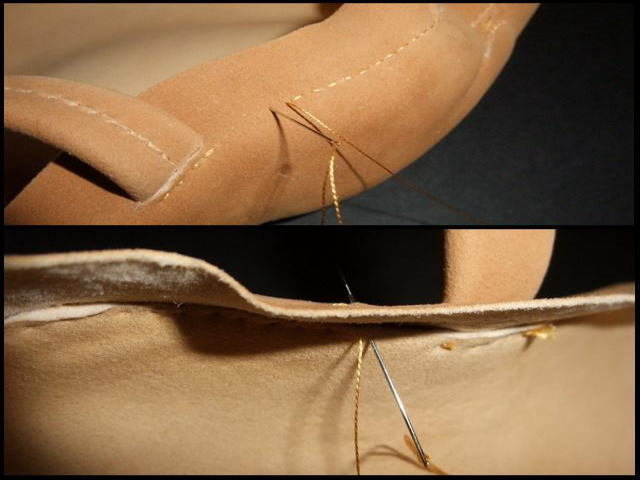 |
控の縁(腕裏部分)を縫い付けます |
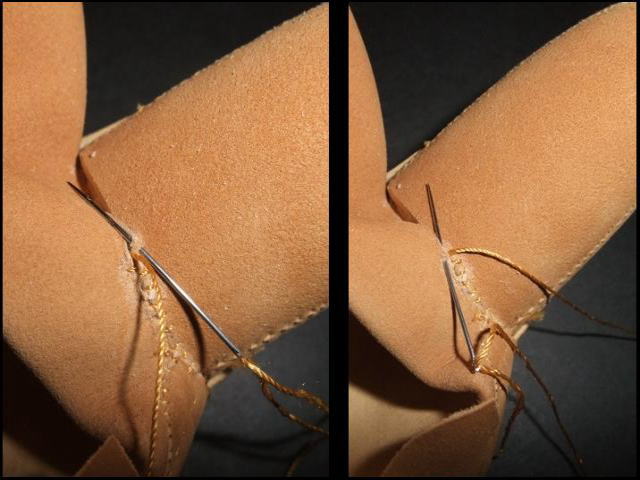 |
台革と拇指(腹側)を縫い付けます |
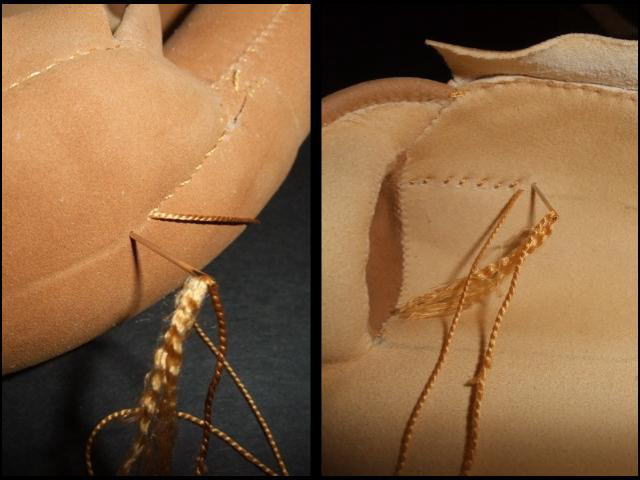 |
一の腰(拇指周り)を縫い止めます
糸の長さが1m弱、一気に縫います
(この部分は朝一番の仕事にしています) |
 |
一通り縫い終わったところ |
 |
副え指取り付け
副え指を取り付けます
副え指の縁も折り返すので、
台革の縁も剥きます
下敷きはガラスです |
 |
剥き終わり |
 |
副え指を台革に合わせ裁断します |
 |
裏を仮止めします |
 |
表を縫い止めます
(突き合わせはぎ縫い) |
 |
裏を縫い止めます
多くは流しまつり縫いですが
表と同じ縫いにしています
予め、綻び止めの糸をセットします
(玉結びを隠すため) |
 |
最後に綻び止めを施します
以上で、副え指の取り付け完了です |
 |
添え指・台革・控えの縁を裏に折り返します |
 |
縁(台革の裏)をまつります |
 |
乳(部品参照)を取り付けます |
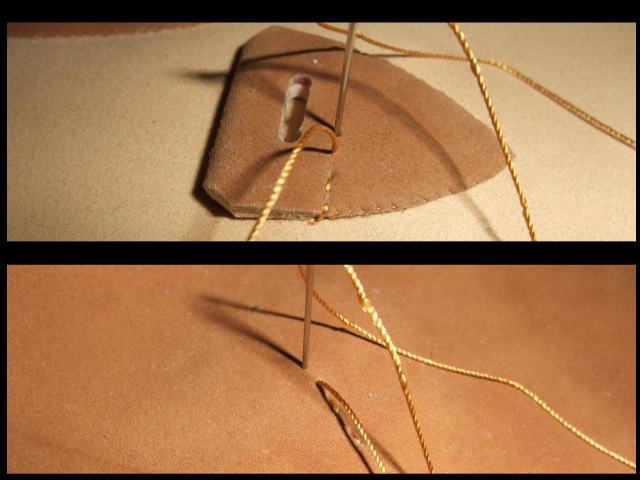 |
上:裏から
下:表から |
 |
手首の寸法に合わせて小紐の長さを決めます |
 |
先端を処理します |
 |
縁、小紐が仕上がったところ |
 |
弦枕(部品参照)を取り付けます |
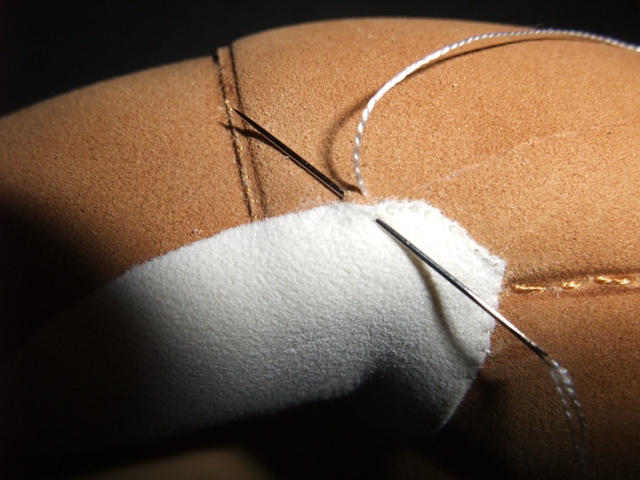 |
腹革・捻り革(部品参照)を取り付けます
周りを縫い付けます |
 |
捻り革の箆受け部分を仕付ます
裏から表へ |
 |
表から裏へ |
 |
腹革と捻り革のつなぎ目を縫い付けます
左から右へ(捻り革) |
 |
右から左へ(腹革) |
 |
縫い付けた部分を…X×X…で補強します
裏から表(捻り革右)へ |
 |
表(腹革左)から裏へ |
 |
裏から表(腹革右)へ |
 |
表(捻り革)から裏へ
これで×が一つ |
 |
腹革を…ヽヽヽ…で補強します
裏から |
 |
表から |
 |
一通り縫い終わったところ
鏝(こて)で縫い目を締めます |
 |
弦枕を固め、銘を入れ、
大紐(部品参照)を取り付ければ完成です |
 |
おまけ(部品参照)
諸般の事情により、2014年3月で、
おまけが無くなりました
|